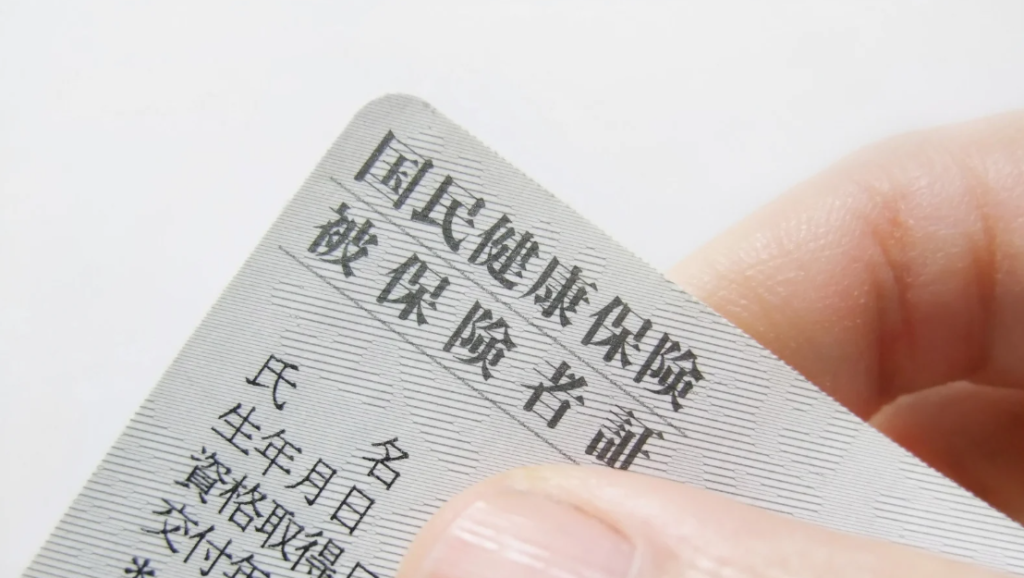
令和7年度 国民健康保険料が引き上げへ!― 改正ポイントと影響をわかりやすく解説 ―
2025年4月から、おもに自営業者が加入する「国民健康保険料」の賦課限度額(上限額)が3万円引き上げとなります。
この改正は少子高齢化による医療費増大に対応するための全国的な国民健康保険料見直しの一環です。今回の改正では年間保険料の賦課限度額(上限額)引き上げが最大の焦点となり、主に高所得者層への負担強化が実施される一方、中間・低所得層への影響は最小限に抑えられる見通しです。
本記事では具体的にどのような変化があるのか、私たちの生活にどう影響するのか?改正の要点をわかりやすく解説します。
国民健康保険料とは
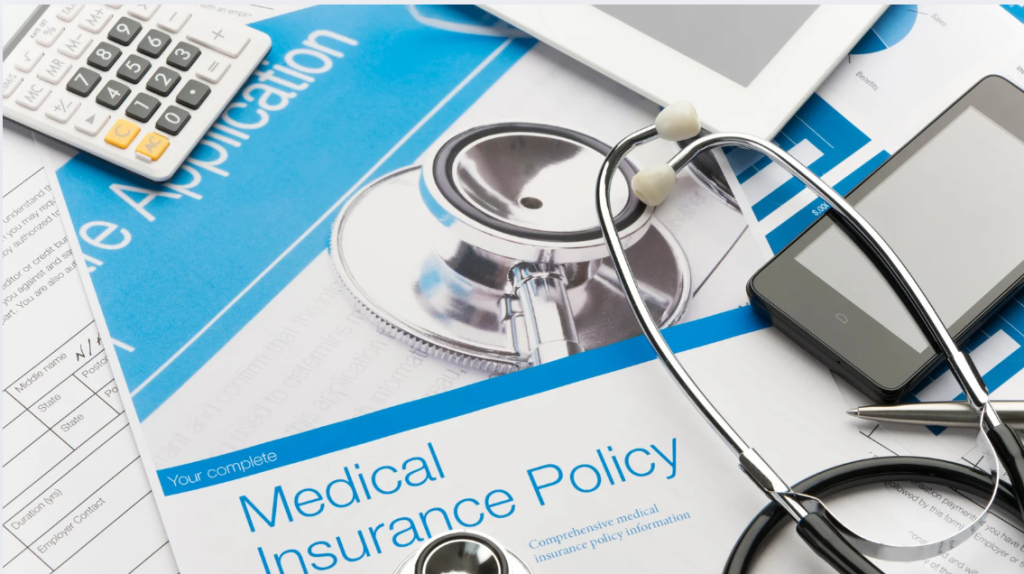
国民健康保険料は、会社員などが加入する「健康保険(社会保険)」とは異なり、主に個人事業主、無職の人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度の保険料です。この保険料は、医療費の財源や高齢者医療、介護保険の費用をまかなうために使われます。
保険料の決まり方
国民健康保険料は、次の3つの要素で構成されます。
- 医療分(基礎分):医療費の財源となる部分
- 支援分:後期高齢者医療制度を支援するための費用
- 介護分:介護保険制度の財源(40歳~64歳の人のみ負担)
計算方式
保険料は「世帯ごと」に計算され、世帯の国民健康保険加入者全員分を合算して世帯主が納めます。計算には主に以下の3つの【所得割】+【均等割】+【平等割】を全部足して、年間の国民健康保険料が決まります。
そして、最終的に計算された保険料が、各市区町村の上限額である賦課限度額を超える場合は、賦課限額までに制限されます。
- 所得割(前年の所得に応じた保険料)
前年の所得金額(収入ではなく、必要経費などを引いた後の金額)に、市区町村ごとに決められた税率をかけて計算します。
- 均等割(加入者1人ごとにかかる保険料)
加入している人数分、定額の保険料がかかります。この金額も、市区町村によって異なります。
- 平等割(世帯単位でかかる保険料)
世帯ごとに一律でかかる保険料です。加入人数には関係なく、世帯単位で1回だけかかります。
なお、福岡市の令和6年度の保険料率・保険料額は以下のとおりです。
国民健康保険料の保険料率(令和6年度 福岡市の場合)
| 区分 | 算定基礎 | ❶基礎分 | ❷支援分 | ❸介護分 |
| 所得割 | 算定基礎となる所得 | 6.20% | 3.46% | 3.02% |
| 均等割 | 1人につき | 20,078円 | 10,334円 | 10.431円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 18,882円 | 9,718円 | 7,912円 |
| 賦課限度額 | 1世帯につき | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
支払い方法と注意点
- 保険料は原則、毎月納付書や口座振替で支払います。
- 年金受給者は年金から天引きされる場合もあります。
- 所得が大きく減った場合や、生活が困難な場合は減免制度もあります。
引き上げの背景と国の狙い

今回の改正は医療費が増え続ける中、制度を維持するため、高所得世帯の保険料上限である賦課限度額を引き上げ、一般の世帯への負担は抑えながら、制度を守る取り組みです。
少子高齢化による医療費増加と財源確保
高齢化社会の進展により、医療給付費が増加の一途をたどっています。国民健康保険の主な加入者は自営業者や無職者など比較的所得が低い層が多く、全体の財源確保が課題となっています
高所得者層への負担強化(年収約1,170万円以上の世帯が主な対象、全体の約1.5%)
今回の上限引き上げは、主に高所得世帯(年収約1,170万円以上)にのみ影響し、全体の約1.5%が該当します。これにより、中間・低所得層の負担増を抑制しつつ、制度の持続可能性を高める狙いです。
日本経済新聞 国民健康保険料の上限3万円上げ決定 厚労省、年109万円
賦課限度額引き上げの概要

令和7年度から、国民健康保険における賦課限度額が引き上げられます。
今回は、中間所得層および高所得層(賦課限度額に到達する世帯)を対象に、収入別の保険料負担がどのように変化するのか、推計データをもとに詳しく解説します。
賦課限度額の変更の内容
まず、各保険料の賦課(課税)限度額は以下のように変更されます。
| 基礎賦課分 | 後期高齢者支援金 賦課分 | 介護給付金賦課分 | 合計 | |
| 引上げ前 | 65万円 | 24万円 | 17万円 | 106万円 |
| 引上げ後 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | 109万円 |
ポイント
医療分・基礎賦課分・後期高齢者支援金等について限度額が引き上げられますが、介護納付金については変更なしとなっています。
収入別の保険料への影響
中間所得層および高所得層(賦課限度額に到達する世帯)を対象に、収入別の保険料負担がどのように変化するのか、厚生労働省の令和4年度の実績データに基づき、予算ベースで令和7年度の状況を推計しました。
中間所得層(年収400万円世帯)の影響
保険料率の引下げにより、限度額引上げ後も全体の負担は軽減されました。具体的には以下のとおりです。
- 年間保険料は限度額引上げ後で 31.9万円 となり、引上げ前の 32.1万円 と比較して 0.2万円の減少。
- 前年度比では 1.0%の増加 となったものの、限度額を引き上げなかった場合と比べると 実際の保険料負担は軽くなっています。
このように、保険料率の引下げが実質的な負担軽減につながっています。
| 引上げ前 | 引上げ後 | |
| 基礎賦課分 | 21.0万円(+1.4%) | 20.9万円(+1.1%) |
| 後期高齢者支援金賦課分 | 8.6万円(+2.8%) | 8.4万円(+1.3%) |
| 介護納付金賦課分 | 2.5万円(+0.7%) | 2.5万円(+0.7%) |
| 合計 | 32.1万円(+1.0%) | 31.9万円(+1.0%) |
高所得層(限度額該当世帯)の影響
限度額の引上げにより、年間保険料に増加が見られました。主な変動要因は次のとおりです。
- 年間保険料は 106万円から109万円へ3万円増加(+2.8%)
- 特に 後期高齢者支援金分が+8.3%と大きく増加
- 基礎賦課分も+1.5%の増加
- 一方で、介護納付金分には変更なし
このように、全体の負担増の背景には、後期高齢者支援金分の増加が大きく影響しています。
| 引上げ前 | 引上げ後 | |
| 基礎賦課分 | 65.0万円(+0.0%) | 66.0万円(+1.5%) |
| 後期高齢者支援金賦課分 | 24.0万円(+0.0%) | 26.0万円(+8.3%) |
| 介護納付金賦課分 | 17.0万円(+0.0%) | 17.0万円(+0.0%) |
| 合計 | 106.0万円(+0.0%) | 109.0万円(+2.8%) |
制度変更の意義
今回の制度変更により、国民健康保険制度の持続可能性と公平性の両立が進められています。
具体的には、高所得者の保険料の上限を引き上げたことで、中間所得層以下の保険料率が引き下げられ、結果的に負担のバランスが改善されました。
ポイント
- 高所得層の限度額引上げにより、中間所得層の負担が軽減
- 保険料率の引下げは、特に中間所得層以下の世帯に恩恵
- 後期高齢者支援金分の限度額引上げ(+2万円)が最も大きな影響
このように、所得に応じた公平な負担を実現しつつ、制度全体の安定化も図られています。
まとめ
令和7年度からの国民健康保険料改正では、主に高所得世帯を対象に保険料の賦課限度額が引き上げられ、年間で最大3万円の負担増が見込まれます。この改正は、少子高齢化に伴う医療費増大への対応として制度の持続可能性を高める目的で実施されるものです。
一方で、中間所得層や低所得層には大きな影響が出ないよう設計されており、年収400万円程度の世帯における保険料は前年からほぼ据え置かれる見通しです。
保険料の増額は高齢化に対応した制度維持の一環であり、全体の財源確保を図りながらも、負担の公平性に配慮した内容となっています。今回の見直しを機に、自身の保険料や支払い方法、減免制度の利用可能性についても改めて確認しておくことが重要です。
